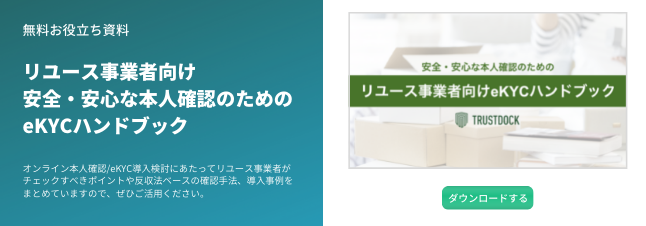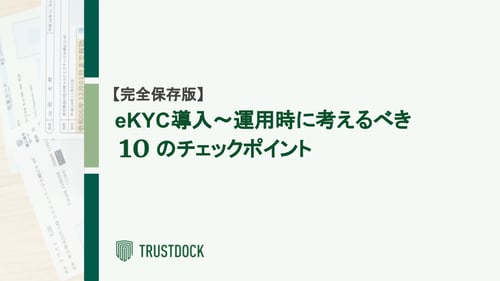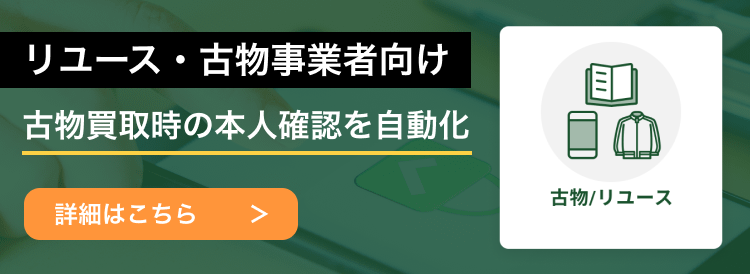シェアリングエコノミーやサーキュラーエコノミーの流れを受け、改めて注目されているリユース市場。特に成長が著しいのが「オンライン・リユース市場」です。環境省の調査報告書によると、ここ数年のオンライン・リユース市場は毎年20%程度の成長を記録しており、2020年以降のコロナ禍をきっかけに非対面での購買活動への機運も一層向上。市場規模はますます拡大することが予想されています。
そんなリユース事業などを営む古物取引商(以下、古物商)にとっての大事なオペレーションの一つが「本人確認」です。これは古物営業法および犯罪収益移転防止法に準拠した義務であり、違反すると営業停止処分はもとより、懲役や罰金刑、場合によっては許可取り消しなどの行政処分を受ける可能性もあります。
一方で各法令に準拠した本人確認業務は、その厳格化によって作業工数が増大しているのも事実。事業者にとっては大きな課題となっています。
本記事では、古物営業法および犯罪収益移転防止法、それぞれの根拠法で提示されている本人確認義務の内容を確認した上で、オンライン・リユース市場を中心にニーズが高まっているデジタルネイティブな本人確認、すなわちeKYCの手法について解説します。
※本記事は、記事公開日時点の情報に基づいて記載しております。
古物商がeKYCを導入するメリット
 eKYCを使った身元確認(後述)の流れの一例
eKYCを使った身元確認(後述)の流れの一例
eKYC(electronic Know Your Customer)とは、スマートフォンやPCなどのデジタルデバイスを使って、オンラインでKYC(本人確認)を行うことを指します。古物商がeKYCを実施すると、以下のメリットが享受できると言えます。
- 本人確認業務のペーパーレス化と店舗依存の解消
- 即日買取の実現による顧客満足度の向上
- 買取時のミスマッチの防止
eKYCを導入すると本人確認がオンラインで完結することになるため、例えば郵送を伴う古物販売において、これまで物品と同梱させていた本人確認用の紙書類を用意する必要がなくなり、事業のペーパーレス化を推進します。
また、店舗を持つような業態においても、現地での本人確認実施に依存する必要がなくなります。そのためユーザーとしては、本人確認目的で営業時間内に店舗に来店する必要がなくなります。
そうなると、本人確認を事前に済ませたユーザーが古物などをオンラインに出品したり店舗に持ち込んだりすることができるようになるので、即日などスムーズな買取が実現し、結果として顧客満足度の向上にも寄与すると言えます。
さらに、例えば宅配便事業者と提携し、古物郵送用のダンボールなどを顧客に届けた上で、所定の宅配便事業者経由で商品の買取を進めるような形態も存在するでしょう。そのようなケースにおいては、例えば配達ドライバーに身分証を提示してもらうという形で本人確認を実施することが想定されますが、もしも玄関先で提示した身分証情報とオンライン登録したユーザー情報が一致しなかった場合、スムーズに商品の授受を進めることができません。それに対してeKYCで事前に住所確認を厳密に実施することで、上記ケースにおけるミスマッチを未然に防止することにもつながります。
このように、古物商がeKYCを導入することで、顧客と事業者の双方にとって大きなメリットがあると言えます。
古物営業法とは?古物商に課された3つのルール

古物営業法とは、中古品やリサイクル品など、古物を取引する際に必要な規制等を定めた法律です。
具体的には以下13種類の品目において、一度使用された物品、未使用でも使用のために取引された物品、もしくはこれらを補修・修理をした物品が、同法の「古物」として定義されています(施行規則第2条第1項1号〜13号)。つまり、以下のケースに当てはまらない食品や電子チケット、化粧品などの物品は、古物営業法における古物に該当しないことになります。
- 美術品類(彫刻、工芸品、書画など)
- 衣類
- 時計・宝飾品類(時計、宝石類、貴金属類、眼鏡など)
- 自動車(タイヤやカーナビなどの部品を含める)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(同様に部品を含める)
- 自転車類(同様に部品を含める)
- 写真機類(カメラ、光学器など)
- 事務機器類(レジ、コピー機、FAX、パソコン、事務用電子計算機など)
- 機械工具類(スマートフォン、医療機器、電機類、工作・土木・化学機械、工具、ゲーム機など)
- 道具類(家具、什器、運動用具、楽器、CD、DVD、ゲーム、トレーディングカードなど)
- 皮革・ゴム製品類(かばん、靴など)
- 書籍
- 金券類(商品券、乗車券、郵便切手など)
これら古物を営利目的で売買・交換取引を反復継続する業態を「古物商」と表現し、盗品などの売買を未然に防止し、発生時には速やかに発見することを目的に制定された法律が「古物営業法」というわけです。
古物商は同法に記されている通り、以下3つのルールを守る必要があります。
- 取引相手の本人確認義務(古物営業法第15条第1項)
- 不正品の申告義務(古物営業法第15条第3項)
- 帳簿の記録義務(古物営業法第16条)
本記事では、この中の「取引相手の本人確認義務」について、詳しく解説していきます。
古物商による本人確認の実施が必要な根拠法

古物商が主に対応するべき根拠法は古物営業法となりますが、実は犯罪収益移転防止法の対応が必要となる場合もあります。以下でそれぞれの根拠法に応じた、本人確認が必要なケースを見ていきましょう。
古物営業法
古物営業法で本人確認が必要とされるのは以下の3ケースです。現金取引のみならず、クレジットカードや電子マネーなどによる取引も対象です。
- 古物を買い受ける場合
- 古物を交換する場合
- 古物の売却または交換の委託を受ける場合
本人確認事項としては「住居」「氏名」「職業」「年齢」の4項目が定義されており、対面と非対面それぞれ複数の方法から任意で確認手段を選択することが可能です(手法詳細については後述)。
なお、取引金額が一万円未満である場合、もしくは同じ物品を売却した相手から買い取る場合は、本人確認は不要とされています。ただし前者について、2018年4月25日公布の改正古物営業法施行規則により、以下の物品においては取引金額に関わらず本人確認が必要となりました。
- 家庭用ゲームソフト
- 自動二輪車および原動機付自動車(部品も含めるが、ネジやボルト等の汎用性部品は除く)
- 書籍
- CD、DVD、BD(ブルーレイディスク)、LD(レーザーディスク)
犯罪収益移転防止法
犯罪収益移転防止法で本人確認が必要とされるのは、貴金属等の売買の業務を行う「古物商」と、流質物である貴金属等の売却を行う「質屋」です。同法では、これら事業者を「特定事業者(宝石・貴金属等取扱事業者)」として指定しており、特定取引等における取引時確認などの義務を課しています。
※特定取引等や取引時確認などについては、以下の記事もあわせてご参照ください。
▶︎犯罪収益移転防止法(犯収法)とは?2025年2月発出パブコメなど、最新トレンドや本人確認/eKYC要件等を解説
ちなみにここでいう「貴金属等」とは、以下の通り貴金属と宝石、ならびにそれらで構成された製品のことを示します。
- 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
- ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
- 上述の貴金属および宝石で構成された製品
具体的な特定取引としては、代金の支払いが現金で200万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結をした場合と定められており、個人の場合は「住居」「氏名」「生年月日」を、法人の場合は「名称」「本店又は主たる事務所の所在地」を、それぞれ本人特定事項として確認する必要があります。
古物営業法に準じた本人確認実務
古物営業法に準拠した本人確認手法としては、以下の13通りが施行規則第15条第3項にて定められています。
特に2018年4月に公布された改正古物営業法施行規則によって、非対面取引における本人確認方法が追加され、物理的な書面の郵送対応のほか、インターネットなどを活用したeKYCによる手法も明記されるようになりました。
※以下の表では各項目の記載事項を要約した上で一覧化しています
| 第1号 | 相手方から印鑑証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受ける |
| 第2号 | 相手方の住所に本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめる |
| 第3号 | 相手方に本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶ |
| 第4号 | 相手方から住民票の写し等の送付、または運転免許証等のICチップ情報の送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱で送付し、その到達を確かめる |
| 第5号 | 相手方から運転免許証/国民健康保険被保険者証等の異なる身分証明書のコピー2点、または身分証明書等のコピー1点と公共料金領収書等(コピーも可)の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる |
| 第6号 | 相手方から住民票等の送付を受け、そこに記載された本人名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶ |
| 第7号 | 相手方から本人確認書類(運転免許証/国民健康保険者証等)のコピー等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付し、その到達を確かめ、あわせてそのコピーに記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結ぶ |
| 第8号 | 古物商が提供したソフトウェアにより、相手方から容貌を撮影した画像の送信を受け、加えて運転免許証等の本人確認書類(写真付のもの)の画像の送信を受ける |
| 第9号 | 古物商が提供したソフトウェアにより、相手方から容貌を撮影した画像の送信を受け、加えて運転免許証等の写真付身分証明書等のICチップ情報(写真を含むもの)の送信を受ける |
| 第10号 | 相手方に目の前で、電子タブレット等に相手方の氏名を筆記させる |
| 第11号 | 相手方から地方公共団体情報システム機構が発行した電子証明書(マイナンバーカードに記載されたもの)と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係る電磁的記録の提供を受ける |
| 第12号 | 相手方から特定認証業務を行う署名検証者が発行した電子証明書と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係る電磁的記録の提供を受ける |
| 第13号 | IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既にとっていることを確かめる |
なお、施行規則第15条第3項第1号「相手方から印鑑証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受ける」について、職業は会社員や自営業といった情報だけでは足りず、具体的な勤務先名称まで確認する必要があります。またここで注意するべきことは、“目の前”で記入していることです。あらかじめ情報が記入された書面では有効にならないので、気をつけましょう。
また、施行規則第15条第3項第10号「相手方に目の前で、電子タブレット等に相手方の氏名を筆記させる」について、スタイラスペンやタッチペンなどのペン型の器具を使用して筆記に当たる行為をさせることが必要で、例えば指を用いたり、電子マウスを操作してその軌跡を相手方の氏名として表示させる方法や、キーボードのキーを操作して氏名を打ち込ませる方法については、認められないので注意が必要です。
犯罪収益移転防止法に準じた本人確認実務

次に、犯罪収益移転防止法に準じた具体的な確認方法を、対面と非対面のケースに分けてご紹介します。改正犯罪収益移転防止法(2018年11月公布・2020年4月1日施行)によって、イ・ロ・ハ・ニ・ホ・ヘ・ト・チ・リ・ヌ・ル・ヲ・ワ・カの計14パターンの手法が定義されました。
なお、古物商が犯罪収益移転防止法に準じた本人確認を行う必要がある場合、古物営業法に準じた本人確認も包含する形でオペレーションを設計しなければならない点に注意が必要です。
| イ | 対面にて写真付き本人確認書類1点の提示 |
| ロ |
対面にて写真なし本人確認書類1点の提示 |
| ハ | 対面にて写真なし本人確認書類2点の提示 |
| ニ |
対面にて写真なし本人確認書類1点の提示 |
| ホ |
専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 |
| ヘ |
専用ソフトウェアにて、写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |
| ト |
専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 or 写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |
| チ |
本人確認書類の原本1点の送付 or 写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 or 専用ソフトウェアにて写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 |
| リ |
本人確認書類2点の送付 or 本人確認書類の写し1点+補完書類1点の送付 |
| ヌ |
※給与振込用口座の開設、または有価証券取引でマイナンバー取得済みの場合が該当 本人確認書類の写し1点の送付 |
| ル | 本人限定郵便(受取時の確認書類は、写真付き本人確認書類である必要ありのもの) |
| ヲ | 電子証明書+電子署名 |
| ワ | 公的個人認証(電子署名) |
| カ | 特定認証業務の電子証明書+電子署名 |
ちなみにTRUSTDOCKでは「ホ」〜「ル」および「ワ」の要件への対応を完了し、eKYCソリューションとして提供をしています。

対面時
まずは店頭などにおける対面時取引での本人確認実務です。具体的には以下の4パターンが列挙されており、先述の法改正以前より明記されてきた施行規則となります。
- 写真付き本人確認書類1点の提示(イ方式)
- 写真なし本人確認書類(健康保険証など)1点の提示 + 転送不要郵便等による到達確認(ロ方式)
- 写真なし本人確認書類2点の提示(ハ方式)
- 写真なし本人確認書類1点の提示 + 住所記載の補完書類1点の送付(二方式)
非対面時
非対面時の本人確認については、先述の改正犯罪収益移転防止法において、郵送不要の新手法と既存手法の厳格化が新たに定義されました。まず、郵送なしの新手法として定義されたのが以下の3パターンです。
- 専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 + 容貌(本人確認時に撮影されたもの)の送信(ホ方式)
- 専用ソフトウェアにて、写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 + 容貌(本人確認時に撮影されたもの)の送信(へ方式)
- 専用ソフトウェアにて、書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信か、写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 + 他の特定事業者の顧客情報の照会(銀行・クレカ情報との照合)か、既存銀行口座への振込(ト方式)
また、郵送ありの手法として厳格化された4パターンとしては以下となります。
- 本人確認書類の原本1点の送付か、写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信か、専用ソフトウェアにて写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 + 転送不要郵便(チ方式)
- 本人確認書類の写し2点の送付か、本人確認書類の写し1点と補完書類1点の送付 + 転送不要郵便(リ方式)
- 給与振込口座の開設、または有価証券取得時に既にマイナンバー取得済みの場合は本人確認書類の写し1点の送付 + 転送不要郵便(ヌ方式)
- 本人限定郵便(受取時の確認書類は、写真付き本人確認書類である必要あり)(ル方式)
この中の「チ」「リ」「ヌ」については、もともとは「本人確認書類の写し1点の送付と転送不要郵便」の対応のみでよかったのですが、2018年公布の改正犯罪収益移転防止法によって、厳格化する形で3つの手法に分化されました。
さらに、それ以外の手法として以下が挙げられます。
- 電子証明書 + 電子署名(ヲ方式)
- 公的個人認証(電子署名)(ワ方式)
- 特定認証業務の電子署名 + 電子署名(カ方式)
古物商でよく使われる本人確認手法4選
上述の通り、古物営業法と犯罪収益移転防止法、それぞれについての本人確認手法が何パターンもあると、どれを選択すれば良いのか判断が難しいのではないでしょうか。ここでは、よく使われる手法4つについてまとめました。
公的個人認証サービス(JPKI)を活用する手法

昨今で最も選択の機運が高まっている手法が、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が提供する公的個人認証サービス(JPKI)を用いた手法です。こちらは、古物営業法においては施行規則第15条第3項第11号に、犯罪収益移転防止法においては施行規則第6条1項1号ワに、それぞれ記載されています。
地方公共団体情報システム機構が提供する公的個人認証サービスは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続きなどを行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を提供するものです。これは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第17条第1項第6号の規定に基づき、総務大臣認定事業者のみ利用が可能となっています。
具体的には、利用者クライアントソフトおよびICカードの読み取り専用デバイス、もしくは読み取り対応スマートフォンアプリを通じて、マイナンバーカードへの電子証明書の記録を行い、その上で公的個人認証サービスを通じてオンライン本人確認を完了させるという流れになります。現在、最も高いレベルのセキュリティによる本人確認とされています。
アプリへの組み込みなど利用ハードルが高い要件ではありますが、TRUSTDOCKによるデジタルIDウォレットのようにスマホでマイナンバーカードが読み取れるアプリがあれば、およそ10秒程度で郵送不要、目視確認不要のeKYCができます。マイナンバーカードを持っているユーザーにとっては対応完了までのスピードが最も早く、事業者側にとっても確認の工数が低く、かつセキュリティ対策が高い手段となっています。
写真付き書類の写し1点+容貌を送信する手法

これまで、古物商で最も多く使われている本人確認手法の一つが、提供したソフトウェアにより相手方から容貌を撮影した画像の送信を受け、写真付きの本人確認書類画像の送信を受けるという手法です(古物営業法施行規則第15条第3項第8号)。
本人確認書類については、運転免許証などであれば表面だけでなく裏面及び厚みの画像の送信を受け、マイナンバーカードであれば表面及び厚みの画像の送信を受けることが必要です(マイナンバーカード裏面には個人番号が記載されているので、送信を受けないように注意する必要があります)。

TRUSTDOCK専用アプリおよびTRUSTDOCKアップローダー(WEB)においては、本人確認書類の表・裏の画像のみならず、カメラの前で書類を傾けるなどして厚みなどを確認するなどの確認フローを設計しています。
また、撮影されたものが正しいとしても、本当にその人がその場で撮影したものなのかを証明する必要もあり、TRUSTDOCKではランダムな英数字を画面上に表示させ(ランダムネスチェック)、それを含めてセルフィー撮影をさせるという処理フローも含めて提供しています。
ICチップ情報の送信+容貌を送信する手法

3つ目は、古物商が提供したソフトウェアにより、相手方から容貌を撮影した画像の送信を受け、加えて運転免許証などの写真付身分証明書等のICチップ情報(写真を含むもの)の送信を受けるという手法です(古物営業法施行規則第15条第3項第9号)。
例えばマイナンバーカードのICチップを使って本人確認を実施する場合、ICチップに格納されている「券面AP」から顔画像を、「券面事項入力補助AP」から基本4情報(※)をそれぞれ抽出します。前者に関してはICチップ内にある顔画像(白黒)とその場で撮影した本人の顔写真を比較・自動判定し、一致率を返却することでなりすましを防止します。
※基本4情報:氏名・生年月日・性別・住所。昨今ではジェンダーアイデンティティへの配慮として「性別」を除外した「基本3情報」を活用する機運が高まっており、たとえば2024年5月27日に施行された改正マイナンバー法では、新しいマイナンバーカードについて、現状のカードに記載されている性別の表記を削除することが盛り込まれました。
公的個人認証サービス(JPKI)を活用する手法に対して、身元確認保証のレベルは下がりますが、ICチップ読み取りによる確認手法であり、またマイナンバーカードの他にも運転免許証や在留カードといった身分証の利用が可能です。
2027年4月1日施行予定の改正犯罪収益移転防止法施行規則の影響
これまでは「写真付き書類の写し1点+容貌を送信する手法」が主流でしたが、偽造身分証による犯罪に巻き込まれるリスク防止の観点から、公的個人認証サービスを使ってマイナンバーカードのICチップを読み取る手法への移行が、犯罪収益移転防止法で定められた特定事業者を中心に進んでいます。
デジタル庁から発表されている方針としても、非対面の方式においては、今後はマイナンバーカードを利用した公的個人認証サービスに一本化し、運転免許証などの画像送信や、顔写真のない本人確認書類を用いる方式は廃止される方針で進んでいます。
それらを反映した改正犯罪収益移転防止法施行規則は、2027年4月1日の施行を予定しており、それに先駆けて2025年2月28日には警察庁からも「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集についてが発出されています。改正の概要としては、以下となります。
- 自然人の本人特定事項の確認方法につき、本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法、本人確認書類の写しの送付を受ける方法を原則廃止(※1)し、マイナンバーカードの公的個人認証に原則一本化(※2)する。
※1:一部法人の被用者の給与等の振込口座の開設等、なりすまし等のリスクが低い類型を除く。
※2: ICチップ付きの本人確認書類(運転免許証等)のICチップ情報の送信を受ける方法等、なりすまし等のリスクが低いものは存置する。
- 法人の本人特定事項の確認方法につき、本人確認書類の原本又は写しの送付を受ける方法について、写しの利用を不可とし、原本に限定する。
- ICチップ付きの本人確認書類を保有しない者等への対応として、偽造を防止するための措置が講じられた一定の本人確認書類(住民票の写し等)の原本の送付を受け、かつ、取引関係文書を転送不要郵便物等として送付する方法を存置するなど、必要な補完措置を整備する。
古物商の中でも、現在の犯罪収益移転防止法施行規則に沿って運転免許証などの画像送信や顔写真のない本人確認書類を用いる方式を採用している特定事業者は、今後、ICチップを用いる方式へと移行する必要があると言えます。
なお、古物営業法に関しては現時点(2025年6月末)において、犯罪収益移転防止法施行規則改正の動きに付随した改正などの動きは見られませんが、今後発生する可能性があります。その際は改めて、本サイトよりご案内します。
本人口座への振込で確認する手法

よく使われる手法、4つ目は、相手に運転免許証などのコピー等と古物を送付してもらい、見積書を転送しない取扱いで簡易書留で送付して、その到達を確かめ、あわせてそのコピーに記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金するという手法です(古物営業法施行規則第15条第3項第7号)。
ここでいう“コピー等”とは、運転免許証などのコピーの他にも、コピーと同程度に鮮明で住所、氏名などの記載内容が読み取れるものであれば、写真データやスキャナーで取り込んだデータ、さらにはそれを印刷した物も含まれます。
また、ここでいう“到達を確める”方法としては、具体的には以下のものがあります。
- 送付した本人限定受取郵便物等(簡易書留等による場合の到達確認も同様。以下同じ)を古物と同封させて返送させる方法
- 本人限定受取郵便物等により受付票等を送付し、当該受付票等を古物と同封させて返送させる方法
- 本人限定受取郵便物等に受付番号を記載して送付し当該受付番号等を相手方から電話、電子メール等により連絡させる方法
- 本人限定受取郵便物等で往復葉書を送付し、その返信部を相手方から送付させる方法
- 本人限定受取郵便物等で梱包材を送付し、その梱包材に梱包して古物を送付させる方法(古物商が送付した梱包材と相手方から送付を受けた古物の梱包材との同一性が判断できるように、自社専用で第三者が入手できない梱包材を使用する。梱包材に個別の番号を付しておくなどの措置が必要です。)
古物商・リユース関連事業者によるeKYC実装事例
最後に、古物商・リユース関連事業者によるeKYC実装例として、TRUSTDOCKを導入した事業者の事例をご紹介します。詳細はそれぞれのコラムをご確認ください。
ブックオフ宅配買取(ブックオフコーポレーション株式会社)

インターネットでの申し込み後にお手持ちのダンボールに品物を箱詰めして、あとは自宅で待つだけで無料で配送業者が集荷に来てくれる「宅配買取サービス」の初回利用時の本人確認手段の一つとして、eKYC/本人確認APIサービス「TRUSTDOCK」を採用しています。
▶︎コスト改善と顧客体験向上の両方を実現:ブックオフコーポレーション様「ブックオフ宅配買取」の事例
【ニーズ】
・郵送による本人確認が抱える課題(本人確認完了までのスピード、オペレーションの煩雑さなど)の解消
・スマホだけでなくPCでの操作も可能な仕組みの構築
・導入直後の運用業務のアウトソース
【導入後の効果】
・本人確認にまつわるトータルコストの改善
・本人確認にまつわる顧客体験の改善(郵送手法と比較した際の対応スピード、オペレーションなどの改善)
ラクウル&おまかせ自動買取くん(株式会社ソフマップ)

買取アプリ「ラクウル」では、買取手続きにおける初回のダンボールの数・集荷日の登録の際に、eKYC/本人確認APIサービス「TRUSTDOCK」を使って本人確認を実施。確認のとれたユーザーだけが、サービスを利用できる仕組みを採用しています。
▶︎リユース・古物買取買の本人確認自動化にeKYC:ソフマップ様事例
▶︎ソフマップ社長が語る、買取アプリ「ラクウル」のオンライン本人確認/eKYC導入の決め手と未来
また、ビックカメラグループの「じゃんぱら」店舗では、お申し込みから精算までの手続きをすべて非対面で完結できるように設計されている「おまかせ自動買取くん」で、AIによる自動査定と並行してTRUSTDOCKの本人確認eKYCが活用されています。
▶︎ソフマップが語る、リユース買取時の本人確認「公的個人認証サービス」の導入効果
ラクウルではホ方式(写真付き書類の写し1点+容貌)とワ方式(公的個人認証サービス)に準拠した仕組みを、おまかせ自動買取くんではワ方式(公的個人認証サービス)に準拠した仕組みを、それぞれ採用いただいています。
【ニーズ】
・顧客による本人確認実施の所要時間の短縮化
・認証失敗率の軽減
【導入後の効果】
・本人確認の承認率の向上
・本人確認の審査の手軽化
・顧客からのスピード感が好評
モバイル機器の下取り事業(Likewize Japan株式会社)

パソコンやスマートフォンのようなITデバイスにおけるエンドユーザーの困りごと(紛失、盗難、損傷、誤動作、アップグレード等)を解決する、BtoBtoCソリューション提供のグローバル企業「Likewize Japan株式会社」では、モバイル機器の下取り事業における郵送による本人確認サービス改善のため、eKYC/本人確認APIサービス「TRUSTDOCK」を導入しました。
▶︎Likewize Japanが語る、モバイル等のオンライン買取でTRUSTDOCKのeKYCを導入した理由と効果
【ニーズ】
・玄関先での身分証確認のミスマッチなど、本人確認失敗時の顧客体験の改善
・届かない返却BOXの輸送費負担の軽減
【導入後の効果】
・本人確認に関するお問い合わせ件数の減少
・コストの大幅削減(ドライバーによる本人確認業務が不要に)
・利便性向上(顧客が不在だった場合の“箱を受け取れない”問題解消による)
TIMELESS AUCTION(株式会社BuySell Technologies)

バッグ・宝石・時計を中心とする日本最大級のBtoBオークションとして、毎週木曜の“平場オークション”と毎月3日〜9日に開催している“オンラインオークション”を開催する「TIMELESS AUCTION」では、入会手続きのタイミングで、eKYC/本人確認APIサービス「TRUSTDOCK」を使った本人確認を実施しています。古物商許可を取得している事業者であれば、原則的にどなたでも参加できるようになっています。
▶︎eKYC導入でBtoBオークションサービスの入会者数が約3倍に増加:BuySell Technologies様の事例
【ニーズ】
・社内の本人確認オペレーションの効率化
・入会時の顧客体験の改善
【導入後の効果】
・ヒューマンエラーリスクが基本的に解消
・本人確認処理期間が2〜3週間から平均4日、最短で当日中の完了に短縮
・従前に比べて月間入会者数がおよそ3倍に増加
効率的なeKYC活用がますます望まれる古物・リユース市場
今回は古物商を営む上で必要な本人確認業務について、古物営業法および犯罪収益移転防止法を根拠法としたポイントを解説しました。
2018年4月に古物営業法が、同年11月に犯罪収益移転防止法が改正され、これまで郵送対応が必要だった本人確認業務にオンライン完結手法が加わり、より効率的でウィズコロナフレンドリーな業務設計が可能となりました。市場規模が拡大の一途をたどる古物・リユース市場だからこそ、効率的なeKYCソリューションの活用がますます望まれると言えるでしょう。
TRUSTDOCKでは、“本人確認のプロ”として企業のKYC関連業務をワンストップで支援するAPIソリューションを提供し、またデジタル身分証のプラットフォーマーとしてさまざまな事業者と連携しております。古物商業務におけるKYC/eKYCおよびDX等でお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。無料の「eKYCハンドブック」もご用意しております。
また、eKYCソリューションの導入を検討されている企業の方々や、実際に導入プロジェクトを担当されている方々のために、TRUSTDOCKではPDF冊子「eKYC導入検討担当者のためのチェックリスト」を提供しております。eKYC導入までの検討フローや、運用設計を行う上で重要な検討項目などを、計10個のポイントにまとめていますので、こちらもぜひご活用ください。
(文・長岡武司)
記事内容の正確性、最新性および網羅性の確保に努めておりますが、本記事の利用により生じたいかなる結果についても、当社は一切の責任を負いかねます。ご利用にあたっては、適宜専門家にご相談の上、ご自身の判断と責任において行ってください。