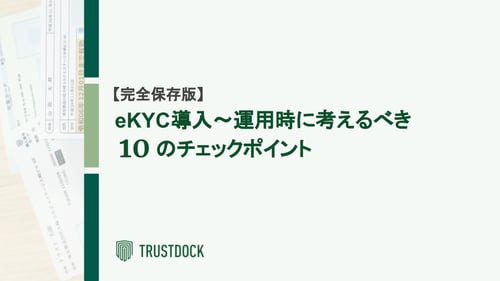日本国内のBtoC-EC市場は年々拡大しており、コロナ禍をきっかけとする非対面での購買活動への機運の高まりも相まって、今後も市場規模はますます拡大することが予想されています。
そんな中、店舗展開と同様にECでの中古品販売および買取に力を入れているのが、ブックオフコーポレーション株式会社様です。今回、同社が展開するブックオフ宅配買取サービスの本人確認時において、TRUSTDOCKの本人確認ソリューションを導入いただきました。
どのような背景でeKYCの導入が検討され、また導入後はどのような効果を体感されているのか。じっくりとお話しを伺いました。
※本記事の内容は取材日時点のものとなります。
本記事のポイント
【ニーズ】
・郵送による本人確認が抱える課題(本人確認完了までのスピード、オペレーションの煩雑さ等)の解消
・スマホだけでなくPCでの操作も可能な仕組みの構築
・導入直後の運用業務のアウトソース
【導入後の効果】
・本人確認にまつわるトータルコストの改善
・本人確認にまつわる顧客体験の改善(郵送手法と比較した際の対応スピード、オペレーション等の改善)
導入サービス:ブックオフ宅配買取
 https://www.bookoffonline.co.jp/files/selltop.html
https://www.bookoffonline.co.jp/files/selltop.html
インターネットでの申し込み後に、お手持ちのダンボールに品物を箱詰めして、あとは自宅で待つだけで無料で配送業者が集荷に来てくれるサービス。集荷から1週間ほどで、買取金額が指定された口座に振り込まれる(振込手数料はブックオフコーポレーションが負担)。本だけでなく、ブランド品やデジタル・家電・楽器、ファッション、ゲームなど、対象商品であればいずれも箱に詰めて売ることができる。
利用しているeKYC本人確認API

✅ eKYC「ホ」
「宅配買取サービス」の初回利用時の本人確認手段の一つとして、eKYC本人確認APIサービス「TRUSTDOCK」を利用しています。
担当者プロフィール

(写真右)菊谷 一郎[Ichiro Kikutani]
ブックオフコーポレーション株式会社
カスタマーコミュニケーション部長
(写真中央)富岡 翔[Sho Tomioka]
ブックオフコーポレーション株式会社
カスタマーコミュニケーション部 ネット買取CSグループ長 兼 CS人財グループ長
(写真左)栗田 優美[Yumi Kurita]
ブックオフコーポレーション株式会社
カスタマーコミュニケーション部 ネット買取CSグループ ネット買取CSチーム
可能な限り店頭と同じようなサービス展開を目指す
--まずは、皆様が所属されるカスタマーコミュニケーション部について教えてください。
菊谷:弊社の中でも、オンラインサービスを利用するお客様に対するサポートを担当しているのが、カスタマーコミュニケーション部になります。現在ブックオフは、全国約800店舗を全都道府県に展開しているのですが、地域によってどうしても店舗数の多い/少ないがあります。近所に店舗が有るか無いかに関わらず、多くの皆さまにブックオフのサービスを使っていただきたいとの思いから、2007年に正式オープンしたのが「公式オンラインストア」です。一般的なECストアと同様、このサイトを通じて商品を購入することができます。また商品の買取についても、可能な限り店頭と同じように多くの皆さまに対応したく、「ブックオフ宅配買取」サービスをサイト内で展開しています。

--部署としては、公式オンラインストアでの商品購入のサポートと、宅配買取サービスのサポートを担当されているわけですね。宅配買取サービスの内容についても教えてください。
菊谷:まずは宅配買取のサイトから無料で集荷予定箱数や日時などをお申込みいただいた上で、読み終わった本などのお品物をお手持ちのダンボールに箱詰めしていただきます。運送会社の手配は弊社の方で行うので、お客様はそのままご自宅等で集荷をお待ちいただくだけで大丈夫です。全国から集荷されたダンボールは神奈川にある弊社物流センターへと集まり、そこで一品ずつ査定を行った上で、買取金額は銀行振込にてお支払いをします。初回の宅配買取申込時に本人確認を行っているので、その際の一つの本人確認手段として、TRUSTDOCKさんのeKYCサービスを使っています。
eKYC以前は、三点一致方式と郵送の2パターンで本人確認を実施
--TRUSTDOCKの運用開始が2023年5月15日ということで、それ以前の本人確認の状況等について教えてください。
菊谷:大きくは2パターンあり、いずれも内製で運用していました。まずレギュラーパターンとして、本人確認書類と集荷先の住所、それから振込先口座の名義が一致しているという「三点一致方式」です。初回の宅配買取を申し込まれたら、ご自身の本人確認書類の画像もアップロードいただくのですが、それだけで本人確認が完了するわけではなく、集荷設定をする際の集荷先住所を入力いただくことで、本人確認書類に記載されている住所と集荷先住所が一致していることも確認します。併せて、買取金額が確定した際の振込先情報も設定いただく際に、本人確認書類に記載されている氏名と口座名義が一致していることも確認します。

菊谷:一方で、レギュラーパターンに該当しないお客様もいらっしゃいます。例えば、コンビニから発送いただく方や、実家に帰省された際に読み終わった本などを整理されて宅配買取を使われるパターンです。この場合、集荷住所と本人確認書類に記載されている住所が異なるので、先ほどお伝えした三点一致方式だと本人確認が弾かれてしまいます。また、例えば振込口座がご主人の口座で本人確認書類が奥様のものというパターンの場合も、今度は名義が一致しないということで、同様に本人確認が完了しません。
--たしかに、イレギュラーなパターンと言いつつ、そこそこの頻度で発生しそうなケースですね。
菊谷:このようなパターンに対しては、古物営業法に定められた郵送による手法で本人確認を実施しています。TRUSTDOCKを導入した現在も、一部運用を残しています。
--日々eKYCに関するご相談をいただいていると、郵便による本人確認は色々とペインがある印象です。
菊谷:おっしゃる通り、弊社とお客様、双方にとってのオペレーションが非常に煩雑であり、本人確認完了までの時間もかかってしまう状況でした。さらに、お客様が一定期間郵送物を受け取ることができなければ、弊社に返送されてしまい、再送の追加コストも発生してしまいます。このような背景から、2020年頃からイレギュラーパターンについてeKYCの導入検討を始めました。
TRUSTDOCKはお客様のPCでも使える、という点が決定的だった

--どのような流れで検討を進めていかれましたか?
菊谷:検討を始めた当初は弊社の方で大きなシステム開発を行う必要がある印象だったのですが、2021年10月に開催されたリユーステックカンファレンスで複数社によるeKYCソリューションの話を伺って、必ずしもそうではないと感じたことから、本格的に導入に向けた問い合わせ等を始めました。
--複数のeKYC事業者の中で、TRUSTDOCKを選定されたポイントを教えてください。
菊谷:何点かあるのですが、まずは業界の中でも最安値の水準でご提供いただけるとのことで、コストの面で魅力的だったことは事実です。それ以上に、提供いただくシステムのUIも非常にシンプルで、使いやすそうだったのが大きかったです。さらに、対応できる本人確認書類の種類が豊富だった点も評価ポイントの一つでした。
そして決定的だったのが、スマホ利用に限定していた他社eKYCと違い「お客様のPCでも使える」という点です。実は弊社の宅配買取サービスは、PCユーザーが結構多いんです。アプリをリリースしてからは多少減ったものの、まだまだ3割ほどはPCからのご利用になっています。PCからも使えるという点は、当時検討した他のeKYC事業者の中にはいなかったと思います。
--複数の観点でありがとうございます。
菊谷:あともう一つ、運用とシステム開発における柔軟性も非常に助かるポイントでした。というのも、本人確認書類の目視作業を行う必要があるのですが、そのための従業員教育やシフト体制の構築などを社内で進めるとなると、それなりに準備期間が必要です。そこもTRUSTDOCKさんが「BPOもできる」とおっしゃるので、導入から1年間はBPOサービスも使わせていただきました。我々が使う管理画面に関しても、他の会社さんだと弊社が作らないといけなかったのですが、TRUSTDOCKさんの場合は提供してもらえますし、ブックオフ仕様にある程度カスタマイズもできるということで、総合的に判断して選定させていただきました。
--導入作業はいかがでしたか?
菊谷:弊社側の開発としては、決まったhtmlタグを挿入してサイトとの結合調整をするだけでしたので、非常にシンプルでわかりやすかったです。2023年2月に開発を始め、同年5月にはサービス開始しているので、非常にスピーディーに導入できたと感じています。
eKYCだと否認率が非常に低く、対応スピードも早い
--現在の、本人確認の運用体制について教えてください。
富岡:買取チームは大きく3つ、電話、メール、手続きや事務作業という3つのユニットに分かれてサポート業務を行っているのですが、その手続きや事務作業を担当しているメンバーが本人確認周りも担当しています。先ほど菊谷からもお伝えしました通り、eKYCスタートのタイミングでは体制が整っていなかったのでTRUSTDOCKさんのBPOサービスを使わせていただいておりましたが、2024年からは内製に切り替え、お客様からの本人確認画像のチェックや否認時の対応等を行っています。
--確認ですが、現在も「三点一致方式」をレギュラーパターンとして採用されていて、eKYCはイレギュラーパターンの選択肢として用意された、ということですよね。
栗田:おっしゃる通りです。お客様のマイページで本人確認を実施する際に、三点一致していない場合は、eKYCの画面に遷移するように仕様を変更しました。
--中長期的にeKYCに集約する、などの選択肢はあるのでしょうか?
富岡:現状は、本人確認手法の選択肢の一つとしてご提供したいと考えています。と申しますのも、eKYCは慣れている方であれば簡単なのですが、ご高齢の方など、スマホやPC操作が苦手な方も多く、全部振り切るとなると選択肢や利便性を損ねる懸念があります。社内での議論も経て現時点では、画像アップロード等による三点一致をレギュラーとして、イレギュラーパターンに対してeKYCと郵送という、大きく3つの選択肢を維持していく予定です。
--実際、eKYCの利用状況はいかがでしょうか?
富岡:具体的な数字はお伝えできないのですが、想定していた以上にお使いいただけているなと感じています。もちろん、従来の郵送による手法を選択されるお客様も一定数いらっしゃいますが、相当減ってきております。何より、eKYCだと否認率が非常に低いので、そこがお客様と弊社の双方にとってありがたいなと感じています。
栗田:もちろん、細かい課題点はまだまだありまして、例えば対応書類としていない健康保険証をアップされる方もいらっしゃいますし、セルフィーの顔を傾けるオペレーションがなかなか伝わらない方もいらっしゃいます。これらについては、TRUSTDOCKさんの機能強化に期待しつつ、非承認時のご連絡の文言を工夫するなどして対応していきたいと考えています。
eKYCは「三方良し」の仕組み
 ブックオフ公式キャラクター「よむよむ君」とともに
ブックオフ公式キャラクター「よむよむ君」とともに
--TRUSTDOCK導入の効果を教えてください。
菊谷:本人確認にまつわるトータルコストが改善できたことが大きいですね。あとなんと言っても、お客様にとって本人確認がより早く済むようになったのも大きいです。郵送による手法と比べると、圧倒的に使いやすくスピーディーになったと実感しています。
--ありがとうございます。それでは最後に、読者の皆さまに一言お願いします。
栗田:同業の古物商をはじめ、どの業界でもeKYCの活用が増えてきている印象です。導入することで、よりサービスとしての融通が効くようになると感じています。
富岡:先ほどもお伝えしたとおり、お客様の選択肢を広げるという観点で、良い手段になっていると感じます。eKYCは、特にタイパ(タイムパフォーマンス)を重視する方にとっての最適な選択肢になっていると思います。
菊谷:私からは導入を検討されている方に向けてとなりますが、eKYCで何を解決したいかを社内できちんとすり合わせてから導入することが、効果の最大化につながると考えています。「流行っているから導入しよう」みたいな動機ですと、もしかしたらうまく使えず、お客様にもフィットしなくて、結果としてコストが増えて顧客体験も損なわれるかもしれません。私自身「コスト改善=お客様の利便性を下げる」ということではないと考えており、eKYCはコスト改善とお客様の利便性向上に加え、カスタマーサポート業務の円滑化を総合的に実現する三方良しの仕組みだと感じているので、しっかりと目的を設定すれば、非常に大きな成果につながると考えています。
---
TRUSTDOCKでは、“本人確認のプロ”として企業のKYC関連業務をワンストップで支援するAPIソリューションを提供し、またデジタル身分証のプラットフォーマーとして様々な事業者と連携しております。eKYCソリューションの導入を検討されている企業の方々や、実際に導入プロジェクトを担当されている方々に向けてはPDF冊子「eKYC導入検討担当者のためのチェックリスト」を提供しており、eKYC導入までの検討フローや運用設計を行う上で重要な検討項目等を計10個のポイントにまとめていますので、ぜひご活用ください。
なお、KYCやeKYCの詳細については、以下の記事も併せてご覧ください。
▶︎KYCとは?あらゆる業界に求められる「本人確認手続き」の最新情報を徹底解説
▶︎eKYCとは?オンライン本人確認のメリットやよくある誤解、選定ポイント、事例、最新トレンド等を徹底解説!
(文・長岡武司)
記事内容の正確性、最新性および網羅性の確保に努めておりますが、本記事の利用により生じたいかなる結果についても、当社は一切の責任を負いかねます。ご利用にあたっては、適宜専門家にご相談の上、ご自身の判断と責任において行ってください。