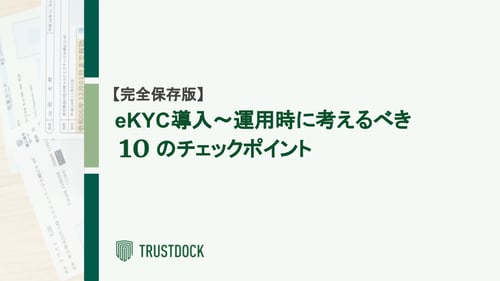ここ一年の間で、いわゆる「闇バイト」に関するニュースが報じられることが急激に増加しています。
闇バイトとは、特殊詐欺の受け子や出し子、強盗の実行犯など、結果として犯罪組織の手先として利用されてしまうような求人案件のことです。その多くはSNSの投稿を中心に募集がかかっていますが、中には闇バイトか否かの区別がつかない形で一般的な求人サイトに掲載されていることもあるとのこと。いずれの場合においても、「短時間で高収入が得られる」「簡単に稼げる」などの甘い言葉に釣られて軽い気持ちで始めたアルバイトが、気づけば犯罪に加担する危険な闇バイトだったというケースが後を絶ちません。
このような状況に対して、2024年11月29日には闇バイト対策の補正予算案として約6億5000万円が盛り込まれるなど、政府の動きも活発になってきています。
そんな中、求人サービス事業者としては、中長期的な闇バイト発生のリスクを未然に防止すべく、具体的にどのような対策を進めればいいのでしょうか。今回は、闇バイト問題を防ぐための法人確認/本人確認の仕組みという切り口で、事業者が実施すべき対策内容について解説します。
※本記事は、記事公開日時点の情報に基づいて記載しております。
闇バイト問題の現状と、官民それぞれの対策状況
警察庁が発行する「2024年版警察白書」では、巻頭に「匿名・流動型犯罪グループに対する警察の取組」という特集・トピックスが組まれています。同庁は匿名・流動型犯罪グループ(以下、匿流)を「SNSを通じて募集する闇バイトなど緩やかな結びつきで離合集散を繰り返す集団」と定義しており、暴力団のような組織統制型の集団ではなく、中核部分が匿名化され、末端メンバーが流動的な点が特徴としています。
匿流は、特殊詐欺や強盗・窃盗、違法なスカウト行為、悪質なリフォーム業、薬物密売など、多様な資金獲得活動を行っており、中でも特殊詐欺については、SNSなどで実行犯を募集し、匿名性の高い通信手段を用いるなどして、証拠を隠滅しようとする傾向があります。近年では、SNS型投資やロマンス詐欺の被害も増加していることから、深刻な社会問題となっています。
 画像出典:匿名・流動型犯罪グループによる犯罪の実行犯の募集手口例(警察庁「2024年版警察白書」3頁)
画像出典:匿名・流動型犯罪グループによる犯罪の実行犯の募集手口例(警察庁「2024年版警察白書」3頁)
2024年4月から5月までの間のデータを見ると、匿流によるものとみられる主な資金獲得犯罪の検挙人数は508人に上っています。その内訳は詐欺が289人、強盗が34人、窃盗が103人となっており、匿流が詐欺を主な資金源としている状況がうかがわれます。
警察庁などの府省庁や、自治体による「闇バイト」対策例
これら匿流による手口に対して、警察庁では部門横断的な体制を構築し、実態解明および以下の取締り施策を強化しています。
- 広域的な捜査連携を強化し、特殊詐欺連合捜査班(TAIT)を都道府県警察に設置
- SNSなどで犯罪実行者を募集する行為への対策として、インターネット・ホットラインセンター(IHC)を運用し、違法情報の排除を図る
- 青少年が安易に犯罪に加担しないよう、教育・啓発活動に注力
- 匿流が悪用する口座や電話、名簿などへの対策
- 暗号資産、電子マネー、フィッシングなどの新たな犯罪への対策の強化
- 繁華街・歓楽街における違法行為の取締りや、スカウトなどの迷惑行為の防止
- 国際捜査の徹底や外国当局などとの連携強化
- 犯罪収益対策として、マネー・ローンダリングの防止や犯罪収益の剝奪の推進
- 高齢者の自宅電話への対策や、現金を自宅に保管させないための対策等の推進
直近では、闇バイトなどに関連するキーワードをSNSで検索した人の画面に、警察からのメッセージ付き広告を自動で表示させるターゲティング広告の事業開始に向けての動きが加速しており、政府の方でもこの事業含む闇バイト対策の予算として、2024年11月29日の閣議決定で約6億5000万円が今年度の補正予算案として盛り込まれています。
また、自治体でも闇バイトに対する取り組みが各所に広がっています。例えば鳥取県では、高齢者世帯が行う防犯対策への助成や、若年層による闇バイトなどを防ぐ啓発のための漫画やSNSの作成・配信などの施策に向けて、補正予算案に約1,400万円を計上しています。
民間企業による「闇バイト」対策例
公的機関の他に、民間企業による対策も着々と進んでいます。例えば求人情報サイトの運営などを手がけるディップ株式会社では、生成AI技術を活用した検知ツール「闇バイトチェック AI」を導入し、目視による闇バイトチェック体制を強化しています。また、ゲーム×教育をテーマに事業展開する株式会社Classroom Adventureでは、「闇バイト」をテーマにしたネットリテラシープログラム「レイの失踪」をリリースし、全国の教育機関や自治体に向けた展開を始めています。
また、一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟の4団体からなる違法情報対応連絡会でも、2023年2月の時点でガイドラインを改訂し、ユーザー契約の際に「闇バイト」など犯罪に関わる書き込みなどを禁じています。
先述の「2024年版警察白書」では、匿流に新たに加担する者への対策の強化も示されており、その中で、求人サイト等での排除についても言及されています。企業としては、闇バイトを募集する違法企業などの排除が喫緊の課題であることがわかります。
 匿名・流動型犯罪グループによる犯罪の実行犯の募集手口例(警察庁「2024年版警察白書」13頁)
匿名・流動型犯罪グループによる犯罪の実行犯の募集手口例(警察庁「2024年版警察白書」13頁)
ペーパーカンパニーが犯罪に利用されやすいという実態
ここまでお伝えしてきた匿流による犯罪に限らず、犯罪集団による「ペーパーカンパニー」の利用は、近年深刻な問題となっています。
ペーパーカンパニーとは、設立されているものの、実際には事業活動を行っていない法人のことを指します。ペーパーカンパニーが存在する理由としては、税務目的やM&Aの手段などさまざまな要因が考えられ、それ自体は決して違法ではないものの、ペーパーカンパニーがマネー・ローンダリングや税金逃れの方法など違法行為の一部として利用されることがあります。例えば2024年5月21日に明らかとなった事件では、実態のない約4000の法人口座が悪用され、700億円の犯罪収益のマネー・ローンダリングとして悪用されたことが報告されています(詳細はこちら)。
実際、一般社団法人 全国銀行協会が定期的に実施している「口座不正利用」に関するアンケート結果によると、口座不正利用に伴う口座の利用停止・強制解約等の件数は、2021年度で54,377件、2022年度で75,621件、2023年度で110,723件と、年々増加していることが分かります(アンケート一覧はこちら)。
 口座不正利用に伴う口座の利用停止・強制解約等の件数の推移について(一般社団法人 全国銀行協会「『口座不正利用』に関するアンケート結果 2024年6月末時点」3頁)
口座不正利用に伴う口座の利用停止・強制解約等の件数の推移について(一般社団法人 全国銀行協会「『口座不正利用』に関するアンケート結果 2024年6月末時点」3頁)
もちろん、利用停止・強制解約などがなされた口座全てが犯罪利用されているわけではありませんが、法人口座がSNS上で違法売買されているケースもあり、ペーパーカンパニーを介した犯罪行為に遭遇するリスクは年々高まっている状況と言えます。
法人確認(対法人向け対応)のデジタル化による予防策
ここまでお伝えしてきた背景より、求人サービス事業者では、求人出稿側となる法人などの厳格な確認が望まれます。ここで、改めて法人確認の以下3つの主要なポイントについて分類して説明します。
- 法人および担当者の存在確認
- 法人および担当者のリスクチェック
- 法人の住所確認
法人および担当者の「存在確認」
「法人の存在確認」とは、取引相手となる法人が架空法人でないか、ちゃんと存在する法人かどうかの確認作業です。
これにはさまざまな方法がありますが、最も簡易的な確認方法としては、国税庁法人番号公表サイトでの検索によるチェックが挙げられます。同サイトでは、対象企業の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号による検索が可能で、検索結果画面ではこの基本3情報に加え、変更履歴情報なども確認できます。
一方で、上記のような基本情報だけでは、本当に実稼働している企業か否かを判断するのは難しいです。よってこれ以上の細かい情報、例えば資本金や事業目的、役員名などを確認したい場合は、一般社団法人民事法務協会(以下、民事法務協会)が提供する「登記情報提供サービス」や東京商工リサーチ、帝国データバンクといった与信管理などを行う情報団体の有料資料を確認する方法もあります。
また、存在確認を行うべきは法人のみならず、契約などを進める担当者も含まれます。担当者が本当に存在する人間なのか、またその組織に所属しているメンバーなのかどうかを確認することで、詐欺による偽装や企業名義の悪用などを防ぎます。前者については、身分証などによる本人確認の実施が望まれます。
法人および担当者のリスクチェック
一般的には、法人および担当者の存在確認とあわせて、その法人や所属するメンバーのリスクの確認も行うケースが多いです。
こちらにもさまざまな方法がありますが、多くの企業では以下のソースを組み合わせて、リスクの確認をし、各社のルールに沿った対応をしています。
- インターネット検索
- 新聞記事データ検索
- 独自の反社会的勢力情報データベースによるチェック
法人の住所確認
「住所確認」はその名の通り、その法人が申請している住所(本社所在地など)でリアルな郵便物が届くかどうかの確認作業です。
法人登録を行う際は各種書類を法務局へ提出することになりますが、実は住所含む記載事項が“正しいか否か”の厳密なチェックは実施されていません。もちろん、記載様式に準拠しているか否かの確認はなされますが、それが実態に即しているかは確認し得ないことになっています。よって、例えばダミーの住所による架空法人を設立すること自体は実は難しいことではありません。
オフィスがきちんと稼働しているか否かは、往復はがきなどによる住所確認が一つの有効な手段となります。
さまざまな角度から法人確認を行うTRUSTDOCKソリューション
TRUSTDOCKでは、それぞれAPI経由でのソリューションを提供しています。いずれも24時間365日の稼働で運用しております。
- 存在確認:法人番号による法人確認API、法人確認業務API、個人身元確認業務API、補助書類確認業務API(委任状)
- リスクチェック:DB検索サービス(記事DB/人物DB)
- 住所確認:郵送業務API(ハガキ)

法人の存在確認
TRUSTDOCKでは法人の存在確認ソリューションとして、大きく2つのAPIを提供しています。
法人番号による法人確認API
これまで事業者が書類をもって法人確認を行う場合、履歴事項全部証明書などを物理的に取得し、郵送で確認する必要がありました。事業者としては郵送という手間やコストが発生する上にサービス利用まで時間がかかるというデメリットがあり、また被確認側であるエンド事業社としても、登記簿を物理的に取得して郵送を受け取る必要があるので、双方にとってのペインポイントが顕著に発生している状況でした。
これに対してTRUSTDOCKでは「法人番号による法人確認API」を提供しています。事業者は法人名と法人番号を提出するだけで、TRUSTDOCKサイドで提出された法人番号をもとに商業・法人登記情報PDFを取得し、申請情報と突合確認し、必要情報一式を返却できるようになっています。

法人確認業務API(謄本提出による法人確認)
もう一つ、該当法人に履歴事項全部証明書を提出してもらい、別途、入力した自社サービスと法人登録情報と突き合わせることで、該当法人の確認を行う手法についてもAPIとしてご提供しています。(履歴事項全部証明書の発行取得業務は代行しておりません)

担当者の存在確認(個人eKYC)
個人の存在確認ソリューションとしても、TRUSTDOCKでは大きく2つのAPIを提供しています。
個人身元確認業務API
担当者が本当に存在する人物なのか、名乗っている人物が本人なのかどうかをチェックする手段として、本人確認をデジタル完結させるeKYCソリューションは有効です。TRUSTDOCKでは犯収法に準拠する各手法をご用意しており、中でも、ワ方式(公的個人認証)とへ方式(ICチップ読取)の導入ケースが増加しています。
ワ方式は、マイナンバーカードのICチップに格納された電子証明書を用いて、成りすまし、改ざん、送信否認の防止を担保し、インターネット上での本人確認や電子申請などを可能とする公的個人認証サービスを使った手法になります。

またへ方式は、マイナンバーカードのICチップに格納されている「券面AP」から顔画像を、「券面事項入力補助AP」から基本4情報をそれぞれ抽出し、前者に関してはICチップ内にある顔画像(白黒)とその場で撮影した本人の顔写真を比較・自動判定し、一致率を返却することでなりすましを防止する手法になります。

ワ方式(公的個人認証サービス利用の手法)に対して、身元確認保証のレベルは下がりますが、ICチップ読み取りによる確認手法であり、またマイナンバーカードの他にも運転免許証や在留カードといった身分証の利用が可能です。
詳細については、以下の記事もあわせてご覧ください。
▶︎公的個人認証サービス(JPKI)とは?「本人確認書類といえばマイナンバーカード」という未来に向けたトレンドを解説
補助書類確認業務API(委任状)
TRUSTODCKでは公的身分証以外の書類(例:公共料金領収書など)を提出していただき、利用者から申請された住所情報などと突き合わせることで、本人かどうかの確認を行うこともできます。例えば現場の担当者が、会社の許可なく勝手に法人アカウントの開設をしていないかなど、委任状の提出にて確認可能となっています。
以下のように、担当者本人の身分証アップに加えて、委任状をアップして確認するフローを設けることも可能です。

委任状の他にも、以下のようなものを補助書類として本人確認に利用可能となっています。(確認する情報項目は、あくまで「氏名/生年月日/住所/性別」の基本4情報のみになります。書類ごとのその他の項目は確認いたしません)
- 住民票
- 広域交付住民票
- 住民記載事項証明書
- 電気料金:支払い領収書
- ガス料金:支払い領収書
- 水道料金:支払い領収書
- 学生証
- 委任状
法人および担当者のコンプライアンスチェック(DB検索サービス(記事/人物))
TRUSTDOCKでは、コンプライアンスチェックソリューションとして「DB検索サービス(記事/人物)」を提供しています。具体的には、氏名、生年月日を使って、各種記事のデータベース(以下、記事DB)で検索・参照し、該当者らしき人物が検索ヒットするか否かを確認するものです。
DBには、先ほどお伝えした新聞記事などの「記事DB」と、反社会的人物をリストアップした「人物DB」があり、このいずれか、もしくはその両方を利用して検索していくこととなります。
個人の場合、全体の90〜97%が外部DBにて該当しないケースが多いため、自社で詳細確認する際にも、本APIで一次チェックすることで時間短縮が可能です。

住所確認(郵送業務API)
該当法人が申請している住所で、リアルな郵便物が届くかどうかの住所確認について、TRUSTDOCKでは「郵送業務API」を提供しています。

具体的には「V折圧着ハガキ」を用いて、申請住所が実在するかのチェック機能を提供しています。それぞれ郵送事業者とAPI連携しているからこそ、スムーズな郵送業務を行なうことができます。

なお、郵便到達の確認方法としてアクティベーションコードの併用も可能となっており、郵送物の中にアクティベーションコードを埋め込むことで、利用者が郵便受け取り後、即時にアカウント開設ができるように設計することも可能です。なおこの場合、アクティベーションコードを失念したり紛失するなどのリスクがある点には留意が必要です。
求人サービス事業者による法人確認の厳格化が求められる時代
記事冒頭でお伝えしました通り、個人への本人確認はもとより、求人サービスへの出稿を希望する法人へのさらなる厳格な確認が、中長期的に望まれる流れとなっていくことが推察されます。このようなトレンドにおいて、確認作業のデジタル化は必須と言えるでしょう。
TRUSTDOCKでは “本人確認のプロ”として、求人サービス事業者をはじめ様々な事業体のKYC関連業務をワンストップで支援するAPIソリューションを提供しており、またデジタル身分証を通じていつでもどこでも、どのような状況でも、身元確認をすることができ、誰でも適切な各種サービスを素早く受け取れる世界を目指しています。
また、日頃から関係省庁・関係団体等と連携し、社内や特定の業界に閉じない議論を行い、今後のデジタル社会に必要なeKYCサービスの提供、社会への情報発信等に積極的に取り組んでいるほか、eKYCサービスに関する新たなルールづくりを進めています。

今回扱った法人確認における業務プロセスのデジタル化についてご不明点がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
なお、eKYCソリューションの導入を検討されている企業の方々や、実際に導入プロジェクトを担当されている方々のために、TRUSTDOCKではPDF冊子「eKYC導入検討担当者のためのチェックリスト」を提供しております。eKYC導入までの検討フローや、運用設計を行う上で重要な検討項目などを、計10個のポイントにまとめていますので、こちらもぜひご活用ください。
(文・長岡武司)
記事内容の正確性、最新性および網羅性の確保に努めておりますが、本記事の利用により生じたいかなる結果についても、当社は一切の責任を負いかねます。ご利用にあたっては、適宜専門家にご相談の上、ご自身の判断と責任において行ってください。