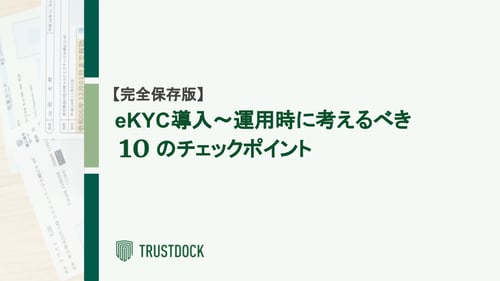近年、EC、宅配サービス、中古品取引、マッチングアプリなど、さまざまなデジタル・プラットフォームが消費者取引の場として急速に普及しています。コロナ禍で加速した「非対面・非接触」の潮流はその後も定着し、現在では生活インフラとして不可欠な存在となっています。
しかし、利便性の一方で、模倣品の流通や商品未着、レビューの信頼性問題、個人情報漏洩、さらには生成AIを悪用した詐欺的な出品・広告表示といった新たなトラブルも増加しています。こうした背景を受け、国内外で法制度の整備とプラットフォーム事業者への規制・要請が強化されています。
本記事では、そんなデジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等について、2021年2月1日施行「透明化法」(正式名称:特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律)や2022年5月1日施行「取引DPF消費者保護法」(正式名称:取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律)の概要と論点、それに対する各種取り組みの内容などを踏まえて解説していきます。
今、問題になっていること
消費者庁が発表するデータによると、消費者が売手となるようなCtoCの電子商取引の市場規模は、直近5年間で約1.5倍に拡大しています。
 画像出典:図表2-14 国内におけるCtoC電子商取引の推定市場規模の推移(消費者庁「2024年9月18日消費者志向経営に関する連絡会資料」)
画像出典:図表2-14 国内におけるCtoC電子商取引の推定市場規模の推移(消費者庁「2024年9月18日消費者志向経営に関する連絡会資料」)
また、デジタルプラットフォームを利用したことがある人のうち、約3人に1人がフリマサイトなどでの出品を経験しています。
 画像出典:図表2-15 フリマサイト等の利用経験・出品経験(消費者庁「2024年9月18日消費者志向経営に関する連絡会資料」)
画像出典:図表2-15 フリマサイト等の利用経験・出品経験(消費者庁「2024年9月18日消費者志向経営に関する連絡会資料」)
一方で、1年以内にフリマサイトなどで買物をした人のうち約2割がトラブルに遭っていることも明らかになっています。
 画像出典:図表2-16 1年以内にフリマサイト等を利用した人のトラブル経験(消費者庁「2024年9月18日消費者志向経営に関する連絡会資料」)
画像出典:図表2-16 1年以内にフリマサイト等を利用した人のトラブル経験(消費者庁「2024年9月18日消費者志向経営に関する連絡会資料」)
トラブルの内容についても確認しましょう。少々古いデータになりますが、以下は売主が事業者である(BtoC取引となる)フリマサイトでの、2018年度における買主からの相談内容の内訳です。
 画像出典:消費者庁「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会 論点整理」p6
画像出典:消費者庁「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会 論点整理」p6
このように見てみると、出品者の債務不履行に関するものが相当数を占めることがよく分かります。
例えば「商品が届かない」件については、出品者の依頼で商品受領前に「評価」をしたことから、商品を受け取れないまま取引が完了してしまうという詐欺的な事案が発生していると言えます。また、事業者が個人を装って、特定商取引法などの規制を免れて模倣品や粗雑品などを販売・流通させているといった相談もあったとのことです。
また、オンライン・ショッピングモールやインターネット・オークションといった業態における、消費者取引に関する買主からの相談内容の内訳が以下です。
 画像出典:消費者庁「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会 論点整理」p5
画像出典:消費者庁「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会 論点整理」p5
こちらでも、出店者の債務不履行に関する相談が半数以上を占めていることが分かります。
例えば「品質に問題がある」とするものについては、出店者が表示する商品説明や写真等と異なるなど、商品表示との相違を問題とするものが挙げられます。
また「その他」については、解約条件や返品に伴う送料トラブル、個人情報管理への懸念、運営事業者等による利用制限への苦情等が挙げられ、出店者との連絡が取れない、もしくは取れなくなったっといった相談も274件にのぼって、数が多くなっている状況です。
消費者庁主催の検討会における基本的視点

これに対して、消費者庁が2019年12月より開催してきたのが「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会」(以下、検討会)です。こちらは、検討会開催時のリリースにおいて、以下の目的が設置されて開催されていたものです。
デジタル市場における消費者利益の確保の観点から、場の提供者としてのデジタル・プラットフォーム企業の役割を踏まえて、消費者被害の実態を把握し、デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等について、産業界の自主的な取組や共同規制等も含め、政策面・制度面の観点から検討する
対象となるデジタル・プラットフォームに対する施策として、具体的に以下の2点が、基本的視点として定められました。
- 消費者の安全・安心を確保する必要性
- 悪質・重大事案への実効性のある取組
消費者の安全・安心を確保する必要性
消費者被害の防止に向けて、まずもってデジタル・プラットフォーム企業に求められることは、以下2点だと検討会冒頭で掲げられています。
- 消費者安全等の視点(違法な製品・事故のおそれのある商品等の流通の防止や緊急時における生活必需 品の流通不安の解消)
- 商品選択時に消費者が合理的判断をするための情報提供の視点(虚偽誇大な広告表示の防止、問題のあるレビューの防止、パーソナルデータのプロファイリングを利用した広告表示の在り方、利用規約の理解促進)
またこれに加え、消費者被害の回復のためには「取引成立後の紛争解決上の不安の解消という視点(デジタル・プラットフォーム企業が関与する紛争解決の仕組み、売主買主間での直接の紛争解決のためのデジタル・プラットフォーム企業の役 割)」も、検討テーマとして有効であるとされました。
なお、こうした取り組みを効果的に推し進め、また並行してデジタル・プラットフォーム企業各社が自主的な取組を行っていたとしても、その内容が消費者に積極的に提供されなければ、トラブル防止の観点でデジタル・プラットフォームを適切に選定できないことになります。よって、上述のような検討会を含めて、官民で協力した情報の開示こそが、今後ますます成長していく市場環境を健全に整備していくことに繋がるともされています。
悪質・重大事案への実効性のある取組
その一方で、例えば違法製品や、事故のおそれのある商品が流通するような事態については、企業の自助努力だけでは対応が難しいのも確かです。これらについては、行政機関による悪質な事業者に対する厳正な取り締まりが必要と言えるでしょう。
特に、どのデジタル・プラットフォーム企業も果たすべき実効的な取り組みを共通ルールとして定めて信頼性を底上げすることはもちろん、悪質な出店者がデジタル・プラットフォーム上の消費者取引の仕組みを悪用する事態や、海外に出店者が存在する事態についても、十分に対応できるものとして整備する必要があります。
JOMC(オンラインマーケットプレイス協議会)の設立

https://www.onlinemarketplace.jp/
このような流れの中、2020年8月に設立された「オンラインマーケットプレイス協議会」(JMOC:Japan Online Marketplace Consortium)は、消費者が安心してデジタル・プラットフォームにおけるオンラインマーケットプレイスで取引できる環境を整えることを目的に設立された団体です。
2025年8月時点で、アマゾンジャパン合同会社、eBay Japan合同会社、auコマース&ライフ株式会社、Bytedance株式会社、株式会社ビビッドガーデン、BASE株式会社、株式会社メルカリ、LINEヤフー株式会社、楽天グループ株式会社の計9社が、会員として参画しています。
2021年2月施行の「透明化法」

これらのトピックにまつわる法規制に目を向けると、2021年2月1日に施行された「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(以下、透明化法)が挙げられます。
透明化法ではデジタル・プラットフォームのうち、特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いプラットフォームを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、規律の対象としています。
特定デジタルプラットフォーム提供者は、取引条件等の情報の開示及び自主的な手続・体制の整備を行い、実施した措置や事業の概要について、毎年度、自己評価を付した報告書を提出することが課されています。
また行政庁としては、上述の報告書などをもとにプラットフォームの運営状況のレビューを行い、報告書の概要とともに評価の結果を公表します。その際に、取引先事業者や消費者、学識者等の意見も聴取して、関係者間での課題共有や相互理解を促し、独占禁止法違反のおそれがあると認められた場合に、経済産業大臣(以下、経産大臣)は公取委に対して同法に基づく対処を要請することになります。
ただし、この透明化法の具体的な規律は、事業分野および規模などの要件を満たすもののうち、さらに特定デジタル・プラットフォーム提供者として経産大臣の指定を受けた企業のみに課されることになります。
これは、この法律が「取引の透明性と公正性の向上を図る」ことに重きが置かれつつも、「デジタル・プラットフォーム提供者が透明性及び公正性の向上のための取組を自主的かつ積極的に行うこと」を基本理念として、国の関与や規制は必要最小限のものとすることと規定している、という考え方に起因しています。
一方で、デジタル・プラットフォームはさまざまな商品や役務、権利の取引の場になっているわけですが、取引に不慣れな人や悪質な事業者であっても売主として容易に参入できるという特性は、プラットフォームの規模や大小に関わらないものだと言えます。
よって、こと「取引」を行うことも主目的とするデジタル・プラットフォームにおいては、その規模や取引の対象によって区別を設けずに対象とすることが適当であると考えられます。
2022年5月施行の「取引DPF消費者保護法」

以上のような背景から、2022年5月1日に施行されたのが「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」(以下、取引DPF消費者保護法)です。
取引DPF消費者保護法は、プラットフォームの規模を問わず、消費者の利益保護に特化した以下の措置を定めています。
- 出品者情報の開示義務:消費者が取引でトラブルに遭った際、プラットフォーム事業者は、悪質な出品者の氏名や住所、電話番号などの情報を消費者に開示することが義務付けられました。これにより、消費者は問題を起こした出品者を特定し、損害賠償などを求めることが可能になりました。
- 不適当な取引への対応:プラットフォーム事業者は、模倣品や粗悪品などの不適切な出品物への対応を強化することが求められます。
こちらは、2021年1月25日に提出された検討会の「報告書案」による、以下の3ポイントを最優先課題と据えて議論が進められたものになります。
- 売主の行政規制違反の防止と、これによる被害救済のためにデジタル・プラットフォーム企業が消費者保護の観点からの措置を講じることが必要となる場合について
- デジタル・プラットフォーム企業が躊躇なくそのような措置を講じられるよう、売主に対して負うこととなる契約上又は法的責任を軽減できるようにしつつ、
- あらゆるデジタル・プラットフォームにおいてそのような取組が確保されることを促進することを最優先課題とすべきであり、その対応のために必要な立法上の措置を講じるべきである
なお、デジタル・プラットフォームには「取引型」と「非取引型」があります。
前者については、先述の透明化法第2条第1項にて規定するデジタル・プラットフォームのうち、BtoCによる通信販売取引が行われる「場」であるもの、すなわち「消費者が通信販売に係る販売事業者等に対して売買契約または役務を有償で契約の申し込みを行うための機能等を有する場」であるものと定義されています。
一方で後者の非取引型とは、直接的な取引の場を提供するわけではないデジタル・プラットフォームを指します。
取引DPF消費者保護法は、前者の「取引型」のデジタル・プラットフォームを主な対象としており、出品者情報の開示義務など、消費者保護のための具体的な措置を課しています。
売主への「法人確認」に対応したeKYCソリューション
このような動きに対して、TRUSTDOCKでは目的や用途に応じた、さまざまな認証強度のeKYCソリューションを提供しています。
例えば、デジタル・プラットフォームにおける売主が株式会社などの法人である場合、取引デジタル・プラットフォーム提供者は、その法人が架空法人ではないか、また反社会的勢力および反市場勢力の疑いがないかなどを確認することが、安心・安全な取引の場における重要なステップとなります。
TRUSTDOCKでは、それぞれAPI経由でのソリューションを提供しています。いずれも24時間365日の稼働で運用しております。
- 存在確認:法人番号による法人確認API、法人確認業務API、個人身元確認業務API、補助書類確認業務API(委任状)
- リスクチェック:DB検索サービス(記事DB/人物DB)
- 住所確認:郵送業務API(ハガキ)

法人の存在確認
TRUSTDOCKでは法人の存在確認ソリューションとして、大きく2つのAPIを提供しています。
法人番号による法人確認API
これまで事業者が書類をもって法人確認を行う場合、履歴事項全部証明書などを物理的に取得し、郵送で確認する必要がありました。事業者としては郵送という手間やコストが発生する上にサービス利用まで時間がかかるというデメリットがあり、また被確認側であるエンド事業社としても、登記簿を物理的に取得して郵送を受け取る必要があるので、双方にとってのペインポイントが顕著に発生している状況でした。
これに対してTRUSTDOCKでは「法人番号による法人確認API」を提供しています。事業者は法人名と法人番号を提出するだけで、TRUSTDOCKサイドで提出された法人番号をもとに商業・法人登記情報PDFを取得し、申請情報と突合確認し、必要情報一式を返却できるようになっています。

法人確認業務API(謄本提出による法人確認)
もう一つ、該当法人に履歴事項全部証明書を提出してもらい、別途、入力した自社サービスと法人登録情報と突き合わせることで、該当法人の確認を行う手法についてもAPIとしてご提供しています。(履歴事項全部証明書の発行取得業務は代行しておりません)

担当者の存在確認(個人eKYC)
個人の存在確認ソリューションとしても、TRUSTDOCKでは大きく2つのAPIを提供しています。
個人身元確認業務API
担当者が本当に存在する人物なのか、名乗っている人物が本人なのかどうかをチェックする手段として、本人確認をデジタル完結させるeKYCソリューションは有効です。TRUSTDOCKでは犯収法に準拠する各手法をご用意しており、中でも、ワ方式(公的個人認証)とへ方式(ICチップ読取)の導入ケースが増加しています。
ワ方式は、マイナンバーカードのICチップに格納された電子証明書を用いて、成りすまし、改ざん、送信否認の防止を担保し、インターネット上での本人確認や電子申請などを可能とする公的個人認証サービスを使った手法になります。

またへ方式は、マイナンバーカードのICチップに格納されている「券面AP」から顔画像を、「券面事項入力補助AP」から基本4情報をそれぞれ抽出し、前者に関してはICチップ内にある顔画像(白黒)とその場で撮影した本人の顔写真を比較・自動判定し、一致率を返却することでなりすましを防止する手法になります。

ワ方式(公的個人認証サービス利用の手法)に対して、身元確認保証のレベルは下がりますが、ICチップ読み取りによる確認手法であり、またマイナンバーカードの他にも運転免許証や在留カードといった身分証の利用が可能です。
詳細については、以下の記事もあわせてご覧ください。
▶︎公的個人認証サービス(JPKI)とは?「本人確認書類といえばマイナンバーカード」という未来に向けたトレンドを解説
補助書類確認業務API(委任状)
TRUSTODCKでは公的身分証以外の書類(例:公共料金領収書など)を提出していただき、利用者から申請された住所情報などと突き合わせることで、本人かどうかの確認を行うこともできます。例えば現場の担当者が、会社の許可なく勝手に法人アカウントの開設をしていないかなど、委任状の提出にて確認可能となっています。
以下のように、担当者本人の身分証アップに加えて、委任状をアップして確認するフローを設けることも可能です。

委任状の他にも、以下のようなものを補助書類として本人確認に利用可能となっています。(確認する情報項目は、あくまで「氏名/生年月日/住所/性別」の基本4情報のみになります。書類ごとのその他の項目は確認いたしません)
- 住民票
- 広域交付住民票
- 住民記載事項証明書
- 電気料金:支払い領収書
- ガス料金:支払い領収書
- 水道料金:支払い領収書
- 学生証
- 委任状
法人および担当者のコンプライアンスチェック(DB検索サービス(記事/人物))
TRUSTDOCKでは、コンプライアンスチェックソリューションとして「DB検索サービス(記事/人物)」を提供しています。具体的には、氏名、生年月日を使って、各種記事のデータベース(以下、記事DB)で検索・参照し、該当者らしき人物が検索ヒットするか否かを確認するものです。
DBには、先ほどお伝えした新聞記事などの「記事DB」と、反社会的人物をリストアップした「人物DB」があり、このいずれか、もしくはその両方を利用して検索していくこととなります。
個人の場合、全体の90〜97%が外部DBにて該当しないケースが多いため、自社で詳細確認する際にも、本APIで一次チェックすることで時間短縮が可能です。

住所確認(郵送業務API)
該当法人が申請している住所で、リアルな郵便物が届くかどうかの住所確認について、TRUSTDOCKでは「郵送業務API」を提供しています。

具体的には「V折圧着ハガキ」を用いて、申請住所が実在するかのチェック機能を提供しています。それぞれ郵送事業者とAPI連携しているからこそ、スムーズな郵送業務を行なうことができます。

なお、郵便到達の確認方法としてアクティベーションコードの併用も可能となっており、郵送物の中にアクティベーションコードを埋め込むことで、利用者が郵便受け取り後、即時にアカウント開設ができるように設計することも可能です。なおこの場合、アクティベーションコードを失念したり紛失するなどのリスクがある点には留意が必要です。
さまざまなデジタル・プラットフォームにフィットしたeKYCを提供
今回はデジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等について、現状の論点と各法律の内容、その他各種取り組みについて解説しました。
TRUSTDOCKは“本人確認のプロ”として、多くの金融機関等犯収法における特定事業者からそうでない民間事業者まで、さまざまなデジタル・プラットフォームにフィットしたeKYCソリューションを提供してきており、またデジタル身分証のプラットフォーマーとして様々な事業者と連携しております。今回言及された新規立法や、これからますます加速するニューノーマルに対応する本人確認のあり方でお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
また、eKYCソリューションの導入を検討されている企業の方々や、実際に導入プロジェクトを担当されている方々のために、TRUSTDOCKではPDF冊子「eKYC導入検討担当者のためのチェックリスト」を提供しております。eKYC導入までの検討フローや、運用設計を行う上で重要な検討項目などを、計10個のポイントにまとめていますので、こちらもぜひご活用ください。
なお、KYCやeKYCの詳細については、以下の記事もあわせてご覧ください。
▶︎KYCとは?あらゆる業界に求められる「本人確認手続き」の最新情報を徹底解説
▶︎eKYCとは?オンライン本人確認のメリットやよくある誤解、選定ポイント、事例、最新トレンド等を徹底解説!
(文・長岡武司)