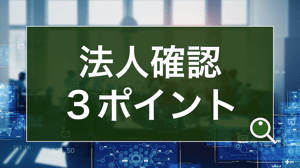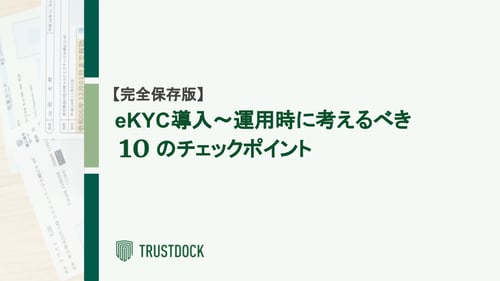DXや業務効率化が叫ばれるなか、「BPaaS(Business Process as a Service、読み方:ビーパース)」という言葉が静かに広まりつつあります。
従来のBPO(Business Process Outsourcing)やSaaSとは異なるこの新しいモデルは、具体的にどんなメリットをもたらしてくれるのか。
本記事では、BPaaSの概要や、BPOとの違い、導入メリット、具体的な活用領域までを解説していきます。
※本記事は、記事公開日時点の情報に基づいて記載しております。
BPaaS(Business Process as a Service)の基本概念

BPaaSという概念を提唱した米調査会社のガートナー社は、以下の通り同語を定義しています。
ガートナーは、BPaaS(Business Process as a Service)を「クラウドから提供され、マルチテナンシー(複数の顧客でリソースを共有する形態)を前提に構築された、BPOサービス」と定義しています。このサービスは多くの場合、自動化されています。人による作業が必要な場合でも、特定の顧客専用の担当者がいるわけではありません。料金モデルは、利用量に応じた課金体系(従量課金制)またはサブスクリプション制です。クラウドサービスであるため、BPaaSモデルはインターネット技術を通じて利用します。
Gartner defines business process as a service (BPaaS) as the delivery of business process outsourcing (BPO) services that are sourced from the cloud and constructed for multitenancy. Services are often automated, and where human process actors are required, there is no overtly dedicated labor pool per client. The pricing models are consumption-based or subscription-based commercial terms. As a cloud service, the BPaaS model is accessed via Internet-based technologies.
この定義にある通り、BPaaSとは、人事や経理といった企業のさまざまなビジネスプロセスを、各種SaaSツールなどのクラウドサービスを活用する形でアウトソーシングできるサービスのことを指します。
単なるITツール・ソフトウェアの提供に留まらず、必要な場合は人的リソースの提供も含める形で、「標準化・自動化された業務プラットフォーム(テクノロジー)」と「専門的な知見を持つ人材(ヒト)」を融合させる形で提供されることが特徴とされています。
なぜ今、BPaaSが注目されるのか?

BPaaSが注目される背景には、日本企業が直面する構造的な課題があります。
まず、労働力人口の減少と採用難が深刻化しており、専門性が求められるノンコア業務においては、採用・育成コストと離職リスクの高さが特に問題となっています。例えば、労務管理や法務チェックなどの業務は専門知識が必要ですが、企業の競争力に直結するコア業務ではありません。こうした業務に専門人材を配置し続けることは、人的リソースの効率的な活用という観点から課題があります。
また、変化し続ける法規制とコンプライアンス要件への迅速な対応が求められています。デジタル化の進展に伴い、個人情報保護法やマネーローンダリング対策など、さまざま様々な規制が頻繁に更新されています。これらの変化に自社だけで対応するには、相当な専門知識と継続的な情報収集が必要となります。
さらに、業務の「属人化」からの脱却が急務となっています。特定の担当者に依存する業務体制は、その担当者の離職時に業務が停滞するリスクを抱えています。また、属人化された業務は標準化が困難で、全社的な生産性向上の妨げとなっています。
SaaSからカスタマーサクセス、それからBPaaSへ

これらの課題を解決すべく、昨今ではさまざまなSaaSツールが登場しています。ソフトウェアをサービスとして利用するSaaSの形態が登場したことで、企業は特定のソフトウェアパッケージをローカルPCへとインストールすることなく、常に最新版を利用できるようになりました。
一方で、ツールの運用は顧客任せになることも多く、「SaaS導入だけでは成果が出ない」という声が増えてきました。そこで、「カスタマーサクセス」という顧客の導入・活用・定着までを伴走する専門組織が誕生することになります。
ただし、価値実現までの伴走はするものの、運用は依然として顧客主導であることが多く、属人化やヒューマンエラーの問題は依然として残る状況でした。
このような経緯から登場した概念が、BPaaSです。機能や業務プロセス、成果提供を一体で提供し、顧客はAPIを繋ぐだけで運用チームを持つ必要がなくなることから、「成果を状態として保証する」ことができる時代へと突入してきました。
BPOサービスとの違い
BPaaSと似た概念で従来から利用されてきたのが「BPO(Business Process Outsourcing)」サービスです。BPOも企業が自社の業務プロセスの一部を外部の専門業者に委託することを指す言葉ですが、以下のような構造的な課題を抱えています。
- 業務要件や規制が変わっても契約改定と再教育が不可欠で、スピーディに変更できない
- ベンダーの定型フローに合わせる必要があり、自社独自プロセスや差別化要件を反映しづらい
- 新規導入/ベンダー変更時は長期プロジェクトになりコストも膨張しがち
- リアルタイムのKPIや品質が見えにくく、管理・監査が難しい
- 人力でのミスや遅延が発生しやすい
- レガシーインフラが固定化され、繁忙期などで柔軟に増減できない
- オフショア拠点での管理により、機密情報漏えい・統制低下の懸念が増大する
- 国・地域ごとの法改正やデータ保護規制に即応しづらい
- 言語やタイムゾーンの違いから連携コストが高く、認識相違が生じやすい
- 低賃金構造により熟練オペレーターの定着が難しく、品質ばらつきと教育コストが増大する etc…
BPaaSは、これらの課題に対する包括的なソリューションとして機能することが期待されています。特に、属人化/ヒューマンエラーなど「人」に起因した課題に対しては、テクノロジー基盤上での業務プロセスの標準化・自動化を志向するため、効率化と品質向上を同時に実現し、企業は限られたリソースをより戦略的な領域へと集中できるようになると言えます。
BPaaSが活かせる業務例

BPaaSが活かせる業務は多岐にわたります。特に、以下のような「定型的」「反復的」「標準化が可能」「スケーラブル」な業務において、BPaaS導入の効果が高いと考えられています。
- 人事・労務関連業務(HR):給与計算、勤怠管理、社会保険手続き、人事データ管理、採用・オンボーディング業務(ATSなどとの連携含む)など
→定期的で標準化しやすく、法改正への対応もBPaaS側に任せられるのがメリットです。
- 経理・財務業務(F&A):請求書処理・発行、支払・入金処理、経費精算、売掛・買掛管理、月次・四半期・年次決算補助など
→定型化された会計業務は自動化・ワークフロー化がしやすく、BPaaSによるコスト削減効果が高い分野です。
- カスタマーサービス/カスタマーサクセス:FAQ・チャットボットによる一次対応、顧客情報の統合管理(CRM)、メール・電話などの問い合わせ処理、アフターサービスやサポートチケットの管理など
→顧客対応の一部業務をクラウド化・自動化することで、オペレーションのスリム化が可能です。
- 法務・コンプライアンス:契約管理、本人確認、コンプライアンスチェック、規制対応・文書管理、訴訟・調査対応支援
→各種コンプライアンス要件への対応を標準化・記録化でき、監査にも有効です。
法務・コンプライアンス領域(リスクチェック、本人確認など)での活用の場合

一例として、法務・コンプライアンス領域におけるBPaaSの活用を考えてみましょう。
法務・コンプライアンス対応は高度な専門知識が求められる一方で、定型的な確認業務も多く存在する領域です。BPaaSの活用により、これらの業務を効率化しながら品質向上を図ることができます。
例えば、新規取引先の登録時に必須となる各種リスクチェック業務は、BPaaSの典型的な活用例です。API連携による各種データベースへの自動照会と、専門オペレーターによる目視確認を組み合わせることで、高精度かつ高速な法人確認などが実現できます。
オンライン本人確認(eKYC)業務に関するソリューションを展開するTRUSTDOCKでも、本人確認にまつわるテクノロジー基盤の提供はもちろん、目視審査や問い合わせ対応、補完依頼、ステータス管理等の実務運用まで一気通貫で対応しています。
特に、24時間365日の確認作業を行うことで、確認精度とスピードを上げて人的・時間的コストを削減し、顧客には「法令に準拠した本人確認が実施されている状態」をそのままご提供しています。
 マイナンバーカードを活用したオンライン本人確認(eKYC)の流れ例
マイナンバーカードを活用したオンライン本人確認(eKYC)の流れ例
またTRUSTDOCKでは、コンプライアンスチェックソリューションとして「DB検索サービス(記事/人物)」を提供しています。具体的には、氏名、生年月日を使って、各種記事のデータベース(以下、記事DB)で検索・参照し、該当者らしき人物が検索ヒットするか否かを確認するものです。
DBには、新聞記事などの「記事DB」と、反社会的人物をリストアップした「人物DB」があり、このいずれか、もしくはその両方を利用して検索していくこととなります。
個人の場合、全体の90〜97%が外部DBにて該当しないケースが多いため、自社で詳細確認する際にも、本APIで一次チェックすることで時間短縮が可能です。

※個人向けのオンライン本人確認(eKYC)や、企業向け法人確認については、以下の記事もあわせてご参照ください。
▶︎eKYCとは?オンライン本人確認を徹底解説!メリット、事例、選定ポイント、最新トレンド等
▶︎あらゆる企業間取引で必要となる「法人確認」とは?3つのチェックポイントについて解説
このように、審査スピードの向上による機会損失の防止はもちろん、チェック漏れリスクの低減や個人情報を自社で保有しないことによるセキュリティリスクの低減などによる、コンプライアンス体制の強化が期待されます。
BPaaSサービス利用時の注意点
BPaaSは多くの企業にとって業務効率化やコスト削減の強力な手段となりますが、当然ながら、導入にあたっては慎重な検討が不可欠です。以下、BPaaSサービス利用時の注意点をお伝えします。
①業務・業界への適合性
まず確認すべきは、自社の業務や業界特有の要件にBPaaSサービスが適しているかどうかです。たとえば、金融・医療・製薬など高度な規制が存在する業界では、業界慣習や法令遵守の知見を持つサービス提供者でなければ対応が難しいケースもあります。
また、業務フローの柔軟性やカスタマイズ性も重要です。パッケージシステムと同様、標準的なサービス内容に縛られすぎると、自社業務にうまくフィットせず逆に効率が落ちてしまう可能性もあります。同業界・同規模の導入実績や事例があるかどうかを確認することも有効です。
②セキュリティ体制やオペレーション品質
セキュリティと運用の信頼性も、欠かせない視点です。特にBPaaSはクラウド上で重要な業務データを扱うため、堅牢な情報セキュリティ体制が求められます。ISO/IEC 27001などの国際的な認証取得状況や、データ暗号化・アクセス制御の仕組みなどを事前に確認しましょう。
また、運用面においても、SLA(サービスレベル合意)による稼働保証や、障害時の迅速な対応体制があるかどうかは、安定運用の観点から非常に重要です。
③導入・運用サポート体制
最後に、導入時および導入後のサポート体制も見逃せないポイントです。BPaaSは単にシステムを導入するだけでなく、業務プロセス全体を設計・調整する必要があるため、事前の業務設計支援やPoC(概念実証)の提供があるかどうかが成否を分けます。
また、導入後もサポート窓口の有無、問い合わせ対応のスピード・品質、障害発生時の連絡ルートの明確さなど、日々の業務に直結する部分の支援体制を重視すべきです。
これらの要素を踏まえ、自社の状況に合ったBPaaSを選定することで、業務プロセス改革の成功へとさらに一歩近づくでしょう。
「人手に頼りがちだった業務」はBPaaS活用の最前線
ここまでお伝えした通り、「業務の仕組みそのものをクラウドに乗せる」ことで、DXの推進はもちろん、コスト削減や品質向上など、一般的な業務委託やBPOなどと比べてより多様なメリットを享受できるのがBPaaSです。
特に、確認や審査、本人特定など「人手に頼りがちだった業務」はBPaaS活用の最前線です。eKYCを含む各種コンプライアンス領域でも、今後ますますBPaaSが欠かせない存在になるでしょう。
本人確認領域のBPaaSをご検討の際は、ぜひお気軽にTRUSTDOCKまでお問い合わせください。
※eKYCソリューションの導入を検討されている企業の方々や、実際に導入プロジェクトを担当されている方々のために、TRUSTDOCKではPDF冊子「eKYC導入検討担当者のためのチェックリスト」を提供しております。eKYC導入までの検討フローや、運用設計を行う上で重要な検討項目などを、計10個のポイントにまとめていますので、こちらもぜひご活用ください。
(文・長岡武司)
記事内容の正確性、最新性および網羅性の確保に努めておりますが、本記事の利用により生じたいかなる結果についても、当社は一切の責任を負いかねます。ご利用にあたっては、適宜専門家にご相談の上、ご自身の判断と責任において行ってください。